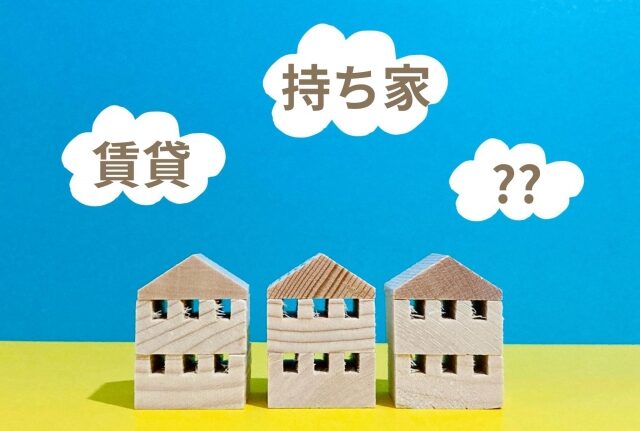60歳以降も働くシニアが増加①|就労意識の変化と法改正のポイントとは?【2025年度版】
60歳を迎えると会社を定年退職し、その後は年金生活に入る――かつてはこれが一般的な働き方でした。
しかし現在では、多くの企業で定年年齢が65歳へと引き上げられ、さらに健康寿命の延びや年金受給開始年齢の引き上げもあり、60歳以降も働き続ける方が増えています。
さらに70歳以降も働きたいと考える人が全体の約半数にのぼるという調査結果もあり、シニア層の就労意識はここ数年で大きく変化してきました。
本記事では、そんな「定年後も働くシニアのリアル」を2回に分けて紹介します。
第1回(本記事)では、シニアの就労意識や働く理由の変化を中心に、定年後も働き続ける背景や70歳までの働き方の実態を解説。
第2回では、「高年齢者雇用安定法の改正」「短時間労働者の社会保険適用拡大」「高年齢雇用継続給付制度」の3つを中心に、2024年以降に行われた法改正と給付制度のポイントをわかりやすく整理してお伝えします。
▶ 60歳以降も働くシニアが増加②|法改正と就労支援制度の最新ポイント
シニア「就労意識」の現状|70歳以降も働きたい人は半数に
現在のシニア層の方は、どのような就労意識を持っているのでしょうか。
株式会社カラダノートが2022年7月15日〜7月20日にかけて実施した「シニア層の就業実態・意識調査(2021年度調査)」によると、「何歳まで働きたいですか?」という質問に対し、以下の結果が出ています。
・70歳以上 18%
・65歳~69歳 17.3%
・60歳~64歳 17.3%
・仕事をしたいと思わない 11.8%
・その他 6.0%
※調査対象:46歳〜80歳の男女244名(男性175名 / 女性69名)
※出典:株式会社カラダノート「シニア層の就業実態・意識調査(2021年度調査)」
「働けるうちはいつまでも働きたい(29.7%)」と「70歳以上(18%)」を合計すると、47.7%になることから、約半数近い方が70歳以降も働く意欲を持っていると考えられます。
「働きたい理由」については、「社会貢献・社会や人との繋がり(40%)」が最も多く、「働くにあたって不安なこと」は、「自分の健康を配慮した環境があるか(47%)」をあげている方が多数を占める結果となりました。
さらに、厚生労働省が公表した「就業構造基本調査(2022年)」や、民間の最新調査(2023〜2024年実施)でも、同様の傾向が見られます。60歳以降も働き続けたいと考える方は依然として多く、特に70歳以降も働きたいと考える人は全体の約半数にのぼっています。
・70歳以上まで働きたい 約20%
・65歳~69歳まで 約15%
・60歳~64歳まで 約15%
・働きたくない/働く意欲はない 約10%
・その他 約5%
※出典:厚生労働省「就業構造基本調査(2022年)」、および民間シンクタンクによるシニア就労意識調査(2023〜2024年実施)
「働きたい理由」としては「収入のため」だけでなく、「社会貢献・人とのつながりを持ちたい」という回答も多く見られます。一方で、「不安」としては「健康面に配慮した職場環境があるか」を挙げる方が増えています。
こうした傾向から、シニア層にとって「働くこと」は経済面の補填に加えて、生活の張りや社会参加の手段としても重要になっていることが分かります。
働き続ける背景にある「経済・社会的な理由」
60歳を超えても働く人が増えている背景には、個人の意欲だけでなく「社会全体の構造変化」も関係しています。
第一に、年金受給開始年齢の引き上げにより、定年後すぐに十分な年金が受け取れない人が増えています。特に自営業や非正規雇用の経験がある人ほど、受給額が少ない傾向にあります。
第二に、物価上昇や長寿化によって「老後資金の不足」が現実的な課題となっており、生活費や医療費のために働き続ける選択をするシニアも多いです。
さらに、社会とのつながりを求めて再就職や地域活動を始めるケースも増加。仕事を通じた生きがいづくりは、健康寿命の延伸にもつながるといわれています。 こうした背景から、近年では「経済的必要性+社会参加の意義」の両面で、働くことを前向きに考えるシニアが増えているのです。
70歳を過ぎても働きたいと考えるシニアが増える一方で、実際に働き続けるには環境整備や制度面の支援が欠かせません。
参照
・厚生労働省・日本年金機構「短時間労働者への社会保険適用拡大について」(2024年改正)
・総務省統計局「就業構造基本調査(2022年)」、民間シンクタンク調査(2023〜2024年)
・厚生労働省「高年齢雇用継続給付のご案内(最新リーフレット、2024年度版)」
 筆者:伊野文明(いの・ふみあき)
筆者:伊野文明(いの・ふみあき)宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。元作家志望であり、落ち着いたトーンの文章に定評がある。
賃貸のことならイチイにお任せ!
サイトに掲載していない物件もご紹介可能です。入居予定日・ご予算・ご希望エリアをご記入のうえ、直接お問い合わせください。人気物件は空室待ち登録で優先的にご案内いたします。