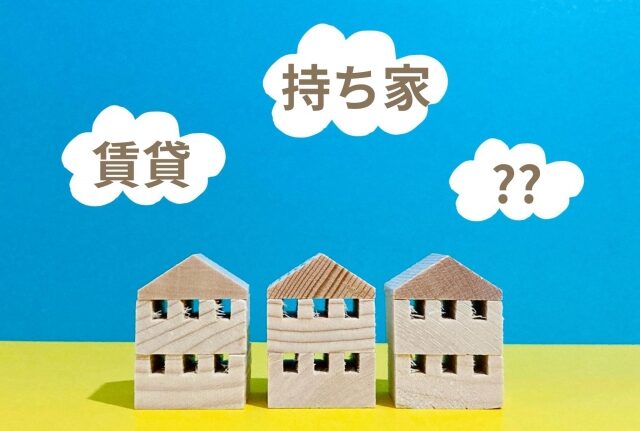60歳以降も働くシニアが増加②|法改正と就労支援制度の最新ポイント【2025年度版】
シニアの就労に関わる法改正の3つのポイント
前回では、60歳以降も働き続けたいシニアが増えてきた背景と、その意識の変化をデータで確認しました。
60歳以降も働くシニアが増加!就労意識の変化と法改正のポイントとは?【2025年度版】
ここ数年、「雇用延長」や「社会保険の適用拡大」など、働き続けたいシニアを支える法改正が次々と実施されています。
特に2024年の改正では、中小企業で働く短時間労働者も社会保険に加入できるようになるなど、働く環境がさらに整いました。
今回はその後編として、2025年度の最新情報にもとづき、「高年齢者雇用安定法の改正」「短時間労働者の社会保険適用拡大」「高年齢雇用継続給付制度」の3つを中心に、制度面から“働くシニア”を支える仕組みを解説します。
1. 高年齢者雇用安定法の改正
高年齢者雇用安定法により、事業主は高齢者が希望する場合、「一定の年齢」まで働き続けられる環境を提供することなどが義務付けられています。
本法律は2012年に「65歳までの雇用確保」を目的とした改正がされ、労働者が希望した場合には65歳まで働ける環境が整備されました。
さらに2021年4月には「70歳までの就業確保」を目的とした改正が行われ、企業には努力義務として対応が求められるようになりました。そのため、大企業を中心に70歳まで働ける環境を整備する企業が増えています。
ただし、65歳から70歳までの期間の就業確保はあくまで努力義務なので、現時点ではすべての企業が必ず70歳まで働ける環境を提供しているわけではない点を理解しておきましょう。
2.短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
70歳近くなると正社員を辞めて勤務時間の短いパート・アルバイトとして働く方法を選ぶ方も少なくありません。
かつては短時間労働者の場合、健康保険、厚生年金保険といった社会保険に加入することが困難でしたが、短時間労働者の社会保険の適用範囲は、この10年ほどで段階的に拡大されてきました。
まず2016年10月の法改正で、従業員501人以上の会社などで働く短時間労働者が、一定の要件を満たせば健康保険や厚生年金保険に加入できるようになりました。
その後、2022年10月には対象が従業員101人以上の事業所にまで拡大され、あわせて雇用期間の見込み要件が「1年以上」から「2カ月を超えて見込まれること」へと緩和されました。
そして2024年10月からは、さらに従業員51人以上の事業所にも適用範囲が拡大。これにより、中小企業で働くパート・アルバイトなどの短時間労働者も、健康保険や厚生年金保険に加入しやすくなりました。
社会保険への加入は、病気やけがで働けなくなった場合の「傷病手当金」や、将来受け取る「厚生年金」の増額にもつながるため、シニア世代にとって大きな安心につながります。
上記を踏まえたうえでの現在の「特定適用事業所」と「短時間労働者が被保険者となる一定の要件」をまとめると、以下の通りです。
特定適用事業所
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時51人以上の事業所。
これまでは「常時100人以上」が対象でしたが、2024年10月の改正で51人以上の事業所にも拡大され、中小企業も対象に含まれるようになりました。
短時間労働者が被保険者となる一定の要件
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
社会保険は給料から天引きされるため、一見損をしているように感じられるかもしれません。
しかし、健康保険へ加入すれば、業務外の病気やけがで働けなくなった時、最長で1年半傷病手当金を受けることができるので、病気や怪我のリスクが上がる高齢の労働者にとっては有効な対策になります。
また、将来受給できる厚生年金も増えるため、人生100年時代と言われる現代においては大きな安心につながります。
ここまで紹介したのは「社会保険加入」に関する制度ですが、このほかにもシニアの就労を後押しする仕組みがあります。その一つが 高年齢雇用継続給付 です。
3. 高年齢雇用継続給付の見直し
「60歳以降も働きたいけれど、収入が減ってしまうのが不安…」そんな声の背景には、定年後に再雇用となる際、給与水準が下がるケースが多いことが挙げられます。
正社員から嘱託・契約社員などの形に変わることで、勤務時間や責任の範囲が軽くなる一方、収入も定年前より2〜4割ほど減るのが一般的です。さらに、在職老齢年金による年金支給の一部調整などもあり、「働いても手取りが減る」と感じる人が少なくありません。
こうした人を支えるのが「高年齢雇用継続給付制度」です。60歳以降に賃金が下がった際、その一部を補ってくれる制度で、現在も多くのシニアが利用しています。
この制度は、60歳以降も働き続ける人のうち、収入が60歳以前より大きく減少した場合に適用されます。具体的には、60歳到達時点の賃金と比較して75%未満に下がった場合に支給される仕組みです。
なお、「高年齢雇用継続給付制度」には次の2種類があります。
①高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降、失業保険などを受給せず、継続して同じ会社で働き続けた場合に受け取れる給付金。退職後に失業保険を受け取っていなければ、再就職した際にも申請できる。
②高年齢再就職給付金
60歳以降、会社を退職して失業保険を受け取り、再就職した際に支給残日数が残っていると受け取れる給付金。
つまり失業保険を受け取っているかどうかで、適用できる給付金の種類が異なります。また、この他にも細かい受給条件があるので、詳細は厚生労働省が公表している「高年齢雇用継続給付についてのリーフレット」から確認するようにしましょう。
この制度は2025年時点でも利用可能ですが、令和7年(2025年)4月1日以降に60歳に達した方 からは、給付率の上限が15%から10%に引き下げられています。今後、制度の在り方については段階的な見直しが検討されています。
70歳以降の就労を見据えた今後の展望
70歳以降も働き続ける方は、今後ますます増えていくと考えられます。
働く期間が長くなることに不安を感じる方もいるかもしれませんが、近年は「生きがい」や「社会貢献」を目的に働くシニアも増えています。法改正の進展により、安心して働ける環境も着実に整いつつあります。
大切なのは、自分の健康状態や生活スタイルに合わせて「無理なく続けられる働き方」を選ぶことです。
フルタイムだけでなく、短時間勤務や在宅ワークなど、ライフステージに応じた多様な選択肢が広がっています。
今後も就労に関する制度改正は続く見込みです。
70歳以降も働き続けたいと考えている方は、最新のニュースや厚生労働省の発表を定期的にチェックしながら、自分らしく、充実したセカンドキャリアを築いていきましょう。
参照
・厚生労働省・日本年金機構「短時間労働者への社会保険適用拡大について」(2024年改正)
・総務省統計局「就業構造基本調査(2022年)」、民間シンクタンク調査(2023〜2024年)
・厚生労働省「高年齢雇用継続給付のご案内(最新リーフレット、2024年度版)」
 筆者:伊野文明(いの・ふみあき)
筆者:伊野文明(いの・ふみあき)宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。元作家志望であり、落ち着いたトーンの文章に定評がある。
賃貸のことならイチイにお任せ!
サイトに掲載していない物件もご紹介可能です。入居予定日・ご予算・ご希望エリアをご記入のうえ、直接お問い合わせください。人気物件は空室待ち登録で優先的にご案内いたします。